第3回業務改革マインドセット勉強会「生成AI×思考の深化~実務と理論の演習~」を開催しました
生成AI、アジャイルの原則、イノベーション理論を学び、業務改革マインドセットを醸成
2025年11月4日(火)に、事務職員を対象とした「生成AI×思考の深化~実務と理論の演習~」を開催しました。
連続する本勉強会では、変化の激しい時代に対応し、より質の高い大学運営を実現するため、職員一人ひとりの意識改革を目的としています。
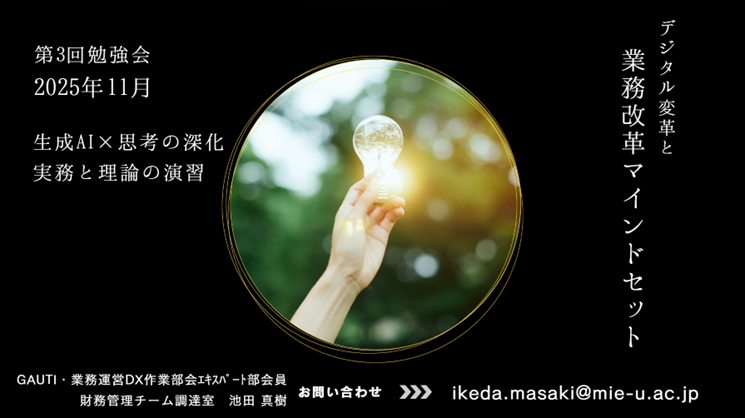
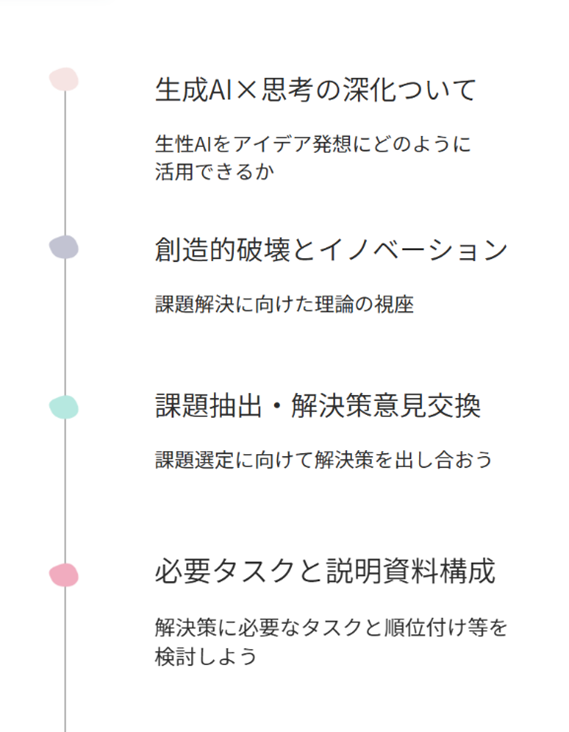

講師は、本学における生成AIの効果的な活用を教職協働で検証・推進する「生成AI活用検証イニシアチブ GAUTI(ゴーチ:Generative AI Utilization and Testing Initiative)」として活動する財務部財務管理チームの池田調達室長が務めました。また、昨年度の受講者(同チーム 舛本主任、土口主任、福田主任)がファシリテーターとして参加し、今年度の受講生のグループワークにおける進行や意見調整を行いました。
表面的な解決策から脱却し、本質的な課題解決の視座に触れる
今回の勉強会は、「生成AIをアイデア発想にどのように活用できるか」、「創造的破壊と新結合、バックキャスト思考」に関する基礎的な理論を学び、「課題解決に向けた俯瞰的な視座」を深めることを主目的として開催されました。
また、前回の学び(「アジャイルの原則」「デザイン思考」「ナッジ理論」といった複数の理論)を振り返りつつ、新たな考え方により物事の見方を深く探求しました。
仮想演習「紙業務からの脱却〜オンライン申請移行〜」を実施
学んだ理論を実務に結びつけるため、「アジャイルの原則・デザイン思考を基にした実務実践演習」として、「紙業務からの脱却〜オンライン申請移行〜」を例にした簡易の仮想演習を実施しました。
参加者は、「アジャイルの原則を意識した、段階的なロードマップ作成(1stリリース、2ndリリースなど)と各リリースに必要なタスクの洗い出し」に取り組み、プロジェクトや改善を実施する際の課題とタスクを具体的に想定しました。
この演習を通じて、最初から完璧を目指すのではなく、利用者の反応を見ながらすばやくリリースを繰り返す「アジャイル」の考え方や、ステークホルダー(関係者)の視点を意識した業務改善プロセスを体験的に学びました。
実業務に直結した「課題抽出・解決策意見交換」
各自が持ち寄った実業務における課題に対して、グループごとに課題の背景やそもそもの考え方などを深掘りした後、課題解決に向け、デジタルツールファースト(デジタルツールの利用をまず最初に検討するという考え方)を前提に参加者同士が意見交換を実施しました。
受講者の声
・他部署の課題とその解決策を聞き、これまでの自分の業務内では思いつかない発想だったので刺激的でした。
・創造的破壊と新結合という考え方をもとに、項目ごとに分解して考えることの大切さに気付くことができた。
・「必要最小限の目的」や「そもそも業務をなくせないか」という視点を再認識しました。
・「なぜ?」の深掘りについては詰問の雰囲気が出ないよう心掛ける必要があるが、実践すると中々に難しいことに気づけた。
今後の展望
次回は、課題解決に向けた行動計画を発表するため、スライドデザインのコツ×生成AIに関する講義とスライド作成、成果発表会を実施する予定です。また、今年度の勉強会に続き、受講者が講師やファシリテーターといった教える立場となることで、今後も学びの灯を繋げ、学びの好循環により組織全体として改革・学びの意識を醸成してまいります。
本一連の勉強会を通じて、職員一人ひとりが、所属部署の課題解決に留まらず、全学的な業務改善の文化を根付かせるための「全体最適」の達成に向けた意識を醸成するとともに、働きがいのある職場とすることを目指します。
<参考>
第1回勉強会のお知らせ記事はこちらをご参照ください。
https://www.mie-u.ac.jp/news/topics/2025/09/post-3787.html
第2回勉強会のお知らせ記事はこちらをご参照ください。
https://www.mie-u.ac.jp/news/topics/2025/10/post-3800.html











