?発見塾 2024年度
| 開催日 | 5月18日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ1F中央保健センター待合ホール |
| テーマ | 「清末の近代国家形成にむけた論争と現代中国」 |
| 講 師 | 三重大学教育学部・教授 大坪慶之 |
19世紀末から20世紀初頭の中国では、近代国家の形成にむけ様々な議論がなされます。その際に焦点となったのは、新国家の政治体制をどうするか、誰が構成員である国民となるのか、どの範囲を領土とするのかといった問題でした。これらは、清王朝の存続とも関わる重要なものです。一方で、現代中国では、国家の「分裂」・「統一」といった話題や民族問題が、マスコミ報道でしばしば取り上げられています。ここで言われる「中国」「中国人」とは、一体何なのでしょうか。それらは中国の近代国家形成と、どのように関係してくるのでしょうか。これらについて、清朝の統治構造、辛亥革命に至る動きを中心に、歴史的に考えてみましょう。


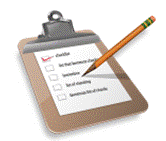 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・昨今の情勢を考え直す良い機会になりました。久しぶりに学び直すことができて非常に興味深かったです。
・大変興味深いテーマを分かり易くご説明いただきました。今日、世界がなんとなく不安と緊張につつまれています。地政学的な問題も含め、その原因の根元を知りたいと思います。なぜ中国は外に力をのばすのか。
| 開催日 | 7月27日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ3F第7会議室 |
| テーマ | 「海のほ乳類,クジラとイルカの世界~身近にどんなイルカがいるか?」 |
| 講 師 | 三重大学大学院生物資源学研究科・准教授 船坂徳子 |
皆さんは水族館,あるいは海に出かけて,クジラやイルカを見たことがありますか?そもそも,クジラとイルカは何が違うのでしょうか.まったく別の動物のような印象があるかもしれませんが,実は両者に明確な区別はありません.30m近くになる大きなシロナガスクジラも,2m程度の小さなスナメリも分類学的には同じグループに含まれていて,体の大きさがだいたい4m以下の種類をイルカ,それより大きな種類をクジラと呼んでいます.この講座では,私たちと同じほ乳類である彼らの体の特徴や暮らし方などを紹介しながら,実は割と身近なところで暮らしているイルカのお話をしたいと思います.

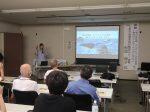
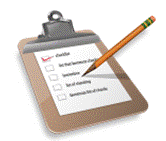 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・伊勢湾の鯨類の実態の解明に三重大学の研究室が努力されている事を知りました。とても興味深くお聞きしました。
・クジラのぬいぐるみ等使ってのお話、楽しくてよく分かりました。子供達若者の参加もありとてもよかったです。
| 開催日 | 9月28日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ1F中央保健センター待合ホール |
| テーマ | 「伊勢エビに何が起こっているか ~海水温上昇がもたらす影響~」 |
| 講 師 | 三重大学大学院生物資源学研究科・教授 松田浩一 |
伊勢えびは、三重県の「県のさかな」に指定され、三重県の優れた産品として「三重ブランド」にも認定される重要な水産資源です。三重県における伊勢えびの漁獲量は、他の多くの水産資源が減少しているのとは対照的に高い水準を保ち、長らく全国一位を誇っていました。しかしながら、近年になって漁獲量が大きく減少し、今後の生産も危惧される状況になっています。その要因として、紀伊半島沖を流れる黒潮の大蛇行等による海水温の上昇があります。伊勢エビは、千葉県以南の黒潮の影響を受ける海域を中心に分布し、本来は温暖な環境を好みます。その伊勢えびが水温上昇でなぜ減少しているのか、その要因について生態も交えて講演します。


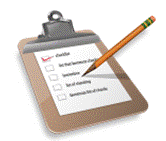 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・子どもが津市内の県立高校に通っており、探求の授業で魚と潮の流れ、温暖化について調べたりしていたため、参考になる事があったのではと思っており参加させていただき良かったと思います。また伊勢エビの様々な事を学べて楽しかったです。
・大潮の大蛇行により、志摩の水温が下がると思っていたが、真逆でおどろいた。さらに、水温の影響が直接イセエビに影響を与えるのではなく、海藻に影響を与え、結果としてイセエビのエビ獲量に影響を与えるということにおどろいた。
| 開催日 | 11月16日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ1F中央保健センター待合ホール |
| テーマ | 「神事・産業・医療用の大麻という植物を正しく知るために -大麻農業・大 麻産業の復活にむけて-」 |
| 講 師 | 三重大学大学院地域イノベーション学研究科、三重大学生物資源学部・教授 諏訪部圭太 |
「大麻」と聞くと皆さん何を思いますか?きっとほとんどの方は薬物に使われる悪い植物というイメージを思い浮かべると思います。しかしそれは、「そういう特徴をもった大麻の種類もある」というひとつの側面に過ぎません。大麻という植物には様々な種類があり、我々日本人にとっては1,000年以上の歴史があるとても大切な植物です。神事や伝統文化、現代・未来社会における大麻の重要性と可能性を正しく理解するために、「大麻とはどういう植物なのか?」「何が良くて何が悪いのか?」「何が正しくて何が間違っているのか?」を皆さんとともに理解したいと思います。


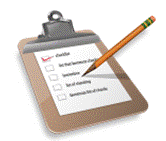 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・大麻の用途を知ることができたので、個人的にもっと調べたいと思えるきっかけになった。大麻の良い側面が世間に広まって、人々の生活が豊かになってほしいと願う。
・麻農業がしたいと思いました。
| 開催日 | 1月11日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ1F中央保健センター待合ホール |
| テーマ | 「新型コロナを振り返り、次に備えるには!」 |
| 講 師 |
三重大学みえの未来図共創機構感染症みらい社会教育研究センター教授・三重大学医学部附属病院感染制御部長 田辺正樹 三重大学医学部附属病院感染制御部師長・感染管理認定看護師 塚脇美香子 |
2020年1月に始まった新型コロナによるパンデミックも、ウィズコロナ時代を経て、2024年4月からは本格的なポストコロナ時代へと突入しました。世界を震撼させ、我々の生活を一変させた新型コロナとは一体何であったのか?次に備えるべき感染症は何か?日本はいったいどこまで準備できているのか?そして、新たな感染症に我々はどのように備えたら良いのか、皆さんと一緒に考えたいと思います。感染対策の専門家より具体的な感染対策についての説明や手洗いチェッカーを用いた手洗い確認の演習もあります。せひ、ご参加ください。


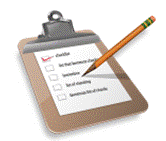 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・医療従事者としての経験、理論、実践の立場から、とても興味深く講義いただきました。これからは手洗いに気を付けます。
・分かりやすい講演でした。侵入門戸の顔をさわらないようにすることが感染対策で必要と知れて良かったです。
| 開催日 | 3月15日(土)【チラシ】 |
| 会 場 | 津リージョンプラザ1F中央保健センター待合ホール |
| テーマ | 「巨大災害にそなえる〜いまやるべきこと〜」 |
| 講 師 | 三重大学工学研究科・教授 地域圏防災・減災研究センター・センター長 川口淳 |
東日本大震災や西日本豪雨災害など,近年災害が激甚化しています。それは地震や台風などの自然現象の大規模化に加えて社会の脆弱性が進行し,被害を大きくしているのです。この地域では南海トラフ巨大地震の発生が危惧されていて,その想定被害の甚大さが国全体として課題になっています。災害対策として大切なのは発災時にどう対応するかはもちろんですが,なによりも災害が起こる前に脆弱性を低くするための対策をしておき,被害を小さくすることです。本講演では,近年発生した災害の事例をもとに,私たちが今やっておくべき対策について考えます。


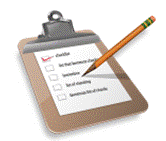 <参加者の声 >
<参加者の声 >
・テレビでは聞けない貴重なお話が聞けました。とても勉強になりました。
・ばくぜんと怖がっていました。水、トイレを中心に備えたいと思いました。











