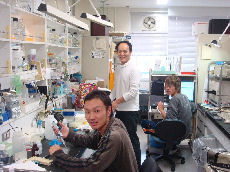鈴木宏治教授、ベルツ賞おめでとう!
~ベルツ博士についても知っておこう~
 11月25日に、第45回ベルツ賞の1等賞に輝いた三重大学大学院医学系研究科病態解明医学講座教授、鈴木宏治さんの研究室を訪れました。鈴木さんの研究室は、総合研究棟Ⅰの4階にあり、伊勢湾を見渡せる眺めのいいところにあります。
11月25日に、第45回ベルツ賞の1等賞に輝いた三重大学大学院医学系研究科病態解明医学講座教授、鈴木宏治さんの研究室を訪れました。鈴木さんの研究室は、総合研究棟Ⅰの4階にあり、伊勢湾を見渡せる眺めのいいところにあります。
研究室を訪れると、大学院生の皆さんや研究員のみなさんが忙しく実験をされていました。さっそく、11月19日に東京のドイツ大使公邸で行われた表彰式で授与された賞状と金メダルや、そして受賞式の写真を見せていただきました。
|
|
|
|
|

|
|
簡単に言えば、鈴木さんは、血がなぜ固まったり、固まらなかったりするのかということを研究しておられるんです。血が固まったり、固まらなかったりするメカニズムは、本当に複雑で、凝固因子というのがたくさんあって、それが順番に反応していくんですが、学生時代にその順番を覚えるのにずいぶん苦労した事を思い出します。
特に鈴木さんはプロテインCインヒビターという凝固に関係する因子の発見者として世界的に有名なのです。今までにも国際血栓止血学会賞(2005.8)、小酒井望賞顕賞(1995.2)、サノフィ国際血栓症賞 (1988.5)など、たくさんの賞を受賞されています。三重大のような地方大学にも世界的な研究者がいることは、ほんとうにうれしいことです。
|
|
|
エルヴィン・フォン・ベルツ博士(Erwin von Bälz, 1849年1月13日 - 1913年8月31日)は、ドイツの医師で、ライプチヒ大学講師の職をなげうって明治9年に来日し、現在の東京大学医学部の前身である東京医学校で教鞭をとられ、27年にわたって医学を教え、日本の医学界の発展に尽くされました。また、草津・箱根を湯泉治療地として開発され、1905年には旭日大綬章を授章されています。
彼の日記や手紙を編集した『ベルツの日記』は、当時の西洋人から見た明治時代初期の日本の様子が詳細に描写されており、たいへん有名ですね。当時、無条件に西洋の文化を受け入れようとする日本人に対して、日本固有の伝統文化の再評価をおこなうべきことを主張されています。
日本の医学はドイツ医学を取り入れ、私の父(95歳の産婦人科医です)の時代にはドイツ語でカルテを書いていたようですが、そのようなルーツもベルツ博士にあるんですね。