研究の概要
生物資源学研究科の諏訪部 圭太准教授が、植物研究のモデル生物であるシロイヌナズナが自身の花粉で子孫(種子)を残す「自殖」へと進化した原因は花粉で機能するたった1個のSCR遺伝子の変異にあり、それがゲノム情報と転写の二段階の変異によるシナジー効果で制御されていることを、東北大学、テキサス工科大学、明治大学、東京大学、チューリッヒ大学、横浜市立大学、大阪教育大学との共同研究により明らかにしました。
生物が絶滅することなく様々な環境に適応していくには、子孫を残す際に遺伝的多様性を維持することが重要です。自ら交配相手を選ぶことができない植物は、自身の花粉で子孫を残す「自殖」ではなく同種他個体の花粉と子孫を残す「他殖」を行うことが大切で、自己・非自己の花粉を認識することで子孫を残すべき花粉を選別する「自家不和合性」という仕組みを有しています。
シロイヌナズナは進化の過程でこの自家不和合性を失い、自身の花粉で子孫を残す「自家和合性」の種(しゅ)へと変化してきましたが、その詳細な進化の道筋は不明でした。なぜシロイヌナズナは自殖性(自家和合性)になったのか?自家和合性への進化にはどのようなことが起きたのか?ということは、この研究のパイオニアであるダーウィンも着目していたものの、その原因は謎でした。
本研究グループは、シロイヌナズナが自家不和合性を失った原因が花粉で機能するSCR遺伝子のコード領域内逆位と転写制御機構にあることを発見し、ゲノム内の遺伝子情報とそれを写しとるための転写機構の二段階でのシナジー効果によって自家不和合性を失う変異が安定化していることを明らかにしました。このことにより、シロイヌナズナの他殖から自殖への進化には自家不和合性を司る鍵遺伝子(SCR)への二重のロック機構が機能していることを見出すとともに、植物生殖の新たな進化仮説を提唱することができ、約150年前にダーウィンが説いた謎にひとつの答えを出すことができました。
本研究成果により、今まで不可能であったモデル生物での自家不和合性研究が可能になるとともに、アブラナ科野菜の品種改良の効率を高めるための基礎研究が飛躍的に発展することが期待できます。
本成果は、2020年9月11日、スイス科学誌「Frontiers in Plant Science」(電子版)に掲載されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
研究者情報
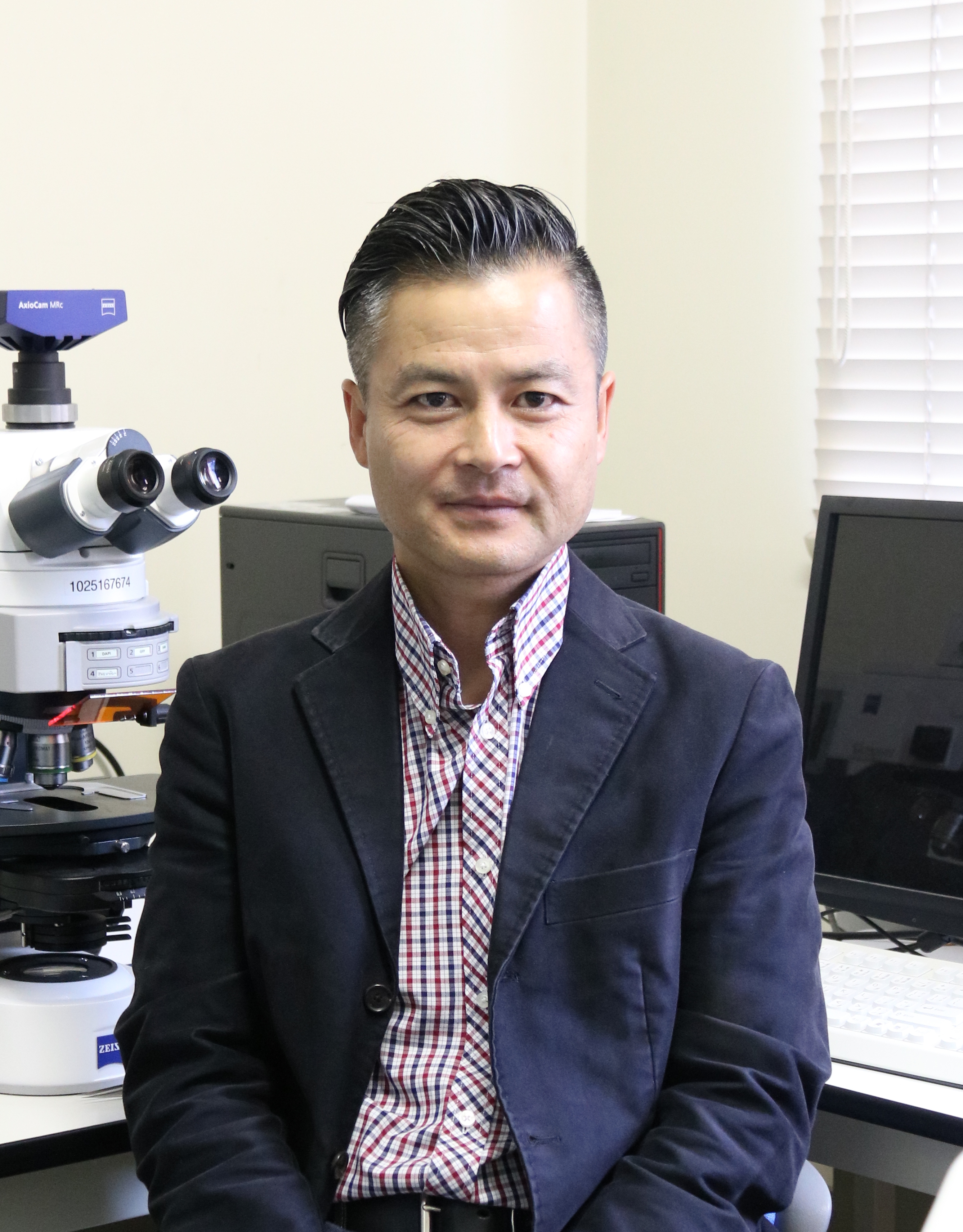
生物資源学研究科 資源循環学専攻 農業生物学 分子遺伝育種学 准教授
諏訪部 圭太 (Suwabe Keita)
専門分野:植物分子遺伝学
現在の研究課題:受粉の分子メカニズム アブラナ科自家不和合性の分子機構