インタビュアー:広報室インターンシップ生(学生)
今回は人文学部法律経済学科の上井長十(うえい たけと)准教授にインタビュー取材を行いました。今回のインタビュアーは、三重大学広報室インターンシップ生(人文学部4年 中川心稜、生物資源学部2年 松下由依)です。(インタビュー日時:2024年9月)

-はじめに、先生の専門分野・研究テーマを教えてください。
上井専門は法律の民法に当たる分野で、主に取引関係や土地の所有に関するルールにまつわる法律を扱っています。特に契約責任についての研究を長年続けています。
-「契約責任」に狙いを絞るようになったきっかけを教えてください。
上井これは少し話が長くなりますが、私が大学生のころに民法ゼミに所属し、担当教員の指導を受けていく中で民法という学問に魅力を感じるようになりました。大学院に進み、民法について深く研究したいなと考えたときに、調べを進めていくうえで出会ったサービス契約をめぐる問題に焦点を当てることにしました。当時はマッサージや医者からの医療行為が思っていたよりも効果がなかった、それは債務不履行だ、契約違反だと主張する論文がしばしばみられました。サービス契約は、お肉や果物とは違い、形のないものであり、実際にサービスを受けてみるまでわからないため、契約違反と認定するのが難しいです。私が大学院生のころは、特にそのようなサービス契約をめぐる契約責任というものが問題視されていたため、研究してみようと考えたのが発端です。
-民法ゼミの財産法ならではの面白みはありますか?
上井日々の日常生活で取引をめぐるトラブルが生じたときに民法を使ってその問題を解決しようとするのが一般的な流れです。しかし、民法は条文が非常に抽象的であるため、問題を解決するためには条文を解釈する必要があります。どのように条文を解釈するかは人によって異なってきます。それに加え、法律は自然科学での法則とは異なり、これはこうあるべきだという「規範」を探していく学問であるため、1つの問題に関して様々な視点について考えながら取り組むことが面白いと感じます。
-先生の現在の研究について教えてください。

上井対価的均衡について現在研究しています。サービスを受けてみたら、「これくらいのサービスしかしてくれないの?」と疑問に感じることがあるかもしれませんが、提供側からすると「我々のサービス提供は本来このようなものである」と主張するため、契約違反にはなりません。契約自由の原則のもとで交わされた契約ではあるのですが、サービスを受けた側は「こんなにお金を払っているのに、、、」と不満を抱いている問題について、本当にこのような現状のままでよいのかと現在研究をしています。
-民法は「物権的視点」と「債権的視点」で事例を解決可能ですか?
上井難しい質問ですね、ザックリと大きくその二つに分けて考える、もしくはその二つが合わさった考え方で解決していくことがほとんどですね。大体はそのように事例を解決していくことが民法での考え方で行くと合理的なのではないでしょうか。
-私は、公序良俗に関する裁判例を時代背景と関連付け、卒業論文を書きたいと考えています。公序良俗はどちらの視点にあたりますか?
上井公序良俗はどちらにも当てはまりそうですね。民法90条には「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められていますが、広く一般の問題として捉えると、物権秩序をめぐる事例やそのときの社会の流れ、一般常識が大きく関わってきますからね。
-条文を解釈していく過程で大切にしていることはありますか?
上井どちらかに肩入れしすぎないように心がけています。裁判でいうところの原告、被告のどちらかに肩入れしすぎないことが民法においては大事です。特別法や弱者の立場を保護する法律でない限り、民法はどちらにもなるべく公平でありながら、解決策を見つけていくことになります。
-民法は身近なものでありながら小難しいものと言われますか?
上井よく身近と言われることがあります、よく考えてみるとあまり身近ではないと私は考えます。土地を購入することも人生で1回あるかどうか、不法行為に巻き込まれることも人生でなかなか起こらないことだと思います。だから勉強する際にもイメージが鮮明に浮かばないから勉強しづらいという側面はあるのかもしれません。
-先生が研究者の道を選んだ理由を教えてください。
上井大学で学んでいた民法が面白いと感じ、「もっと勉強したい」と思ったことや、大学4年生のときが就職氷河期であったことから大学院に進学することを決めました。大学院へ進学した後に学び始めたフランス法で、フランス法特有の法の見方に惹かれたので、研究者の道に進むことにしました。
-研究をしていく中で壁に当たることはありますか?また、壁に当たったときはどのように対処しますか?
上井自分の示す考え方は、本当に「公平」なのか、自分の考え方によってどこかに悪影響をもたらしてしまわないかなど、慎重に考えすぎて前に進まなくなることがあります。そういうときは、研究者同士で定期的に行う研究発表で、ほかの研究者の反応を見たり、意見を聞いたりすることで前に進むヒントを得ています。
-もし、もう一度人生をやり直せるとしたら同じ道を進みますか?
上井選択肢の一つにはなると思います。なぜなら、理系分野にも関心があったからです。ただ今の研究者の道も楽しいので、選択肢の一つとします。
-どのような学生と一緒に研究をしたいですか?
上井民法が得意でなくても、アルバイトやサークルなど色々な経験をしている学生や、自分なりの考え方を持っている学生です。こういった学生とゼミの活動で意見交換をしたり、話したりすることが楽しいです。
-人生の先輩として学生にアドバイスをお願いします。
上井色々な活動をしつつ、勉強の面でも自分の専攻分野を「粘り強く」とことん突き詰めてほしいです。途中で飽きずに、つまずいたとしても諦めずに「粘り強く」勉強を頑張ってほしいです。
研究者情報
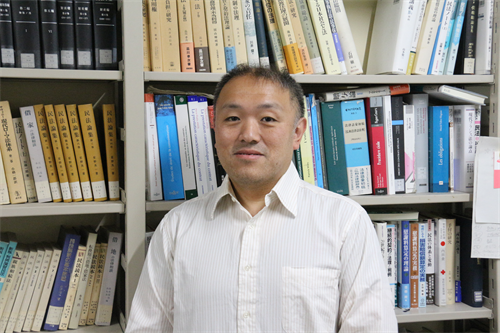
人文学部 法律経済学科
准教授 上井 長十(UEI,Taketo)
専門分野:契約法
現在の研究課題:契約関係のおける当事者の一方的な権限行使
【参考】
人文学部HP https://www.human.mie-u.ac.jp/
教員紹介ページ(上井 長十) https://kyoin.mie-u.ac.jp/profile/1045.html