インタビュアー:みえみえ学生広報室の学生
今回は人文学部法律経済学科の野崎哲哉(のざき てつや)教授にインタビュー取材を行いました。今回のインタビュアーは、みえみえ学生広報室員(人文学部3年 裏川朱音)です。

-はじめに、野崎先生の専門分野・研究テーマについて教えてください。
野崎専門分野は、金融論・銀行論研究です。金融のあるべき姿、規制のあり方、金融業、とりわけ銀行の社会的役割について研究しています。
大学院では現代資本主義における銀行資本の行動分析からスタートしました。都市銀行の行動分析を行いつつ、日本の金融資本研究、企業集団研究へと広げていく予定でした。
しかしながら、大学院博士課程在籍時にバブル経済崩壊による銀行の経営破綻を目の当たりにし、研究計画は大きく変化していくことになりました。今から約30年前の1994年の三重大学への赴任後は、バブル経済崩壊後の金融システム不安への対応、とりわけ不良債権問題の研究へとシフトし、日本の金融界全体を巻き込んだバブルの負の側面を取り扱うことになりました。
一方、当初の研究計画の流れから、1996年以降の金融ビッグバンに伴う金融システム改革の研究、その中での銀行資本の能動的対応についての研究も並行して行いました。2000年代に入り、新自由主義的金融改革が企図され、「マネーゲーム」礼賛的風潮が蔓延する中、リーマンショックが起こりました。新自由主義的金融改革の批判的検討に加え、疲弊する地域金融機関の検討や協同組織金融のあり方の研究も行うことになりました。
こうした金融に関するネガティブな話題が蔓延する中で、今から20年前に、銀行の公的な性格、公共性に関する研究を行いました。さらに、最近では金融分野への情報技術革新の影響も含め金融業総体のあり方を視野に入れた研究を行うとともに、国が力を入れ始めている金融教育のあり方についても研究を広げています。
-研究をしていく中でおもしろいと感じるのはどのような時ですか。

野崎なかなか今の金融の研究をおもしろいとは感じにくいです。金融分野は変化が激しすぎて、ついていくのがやっとということが多いのと、そもそも知りたい情報やデータの多くが秘匿されており、マクロ的な金融動向の分析はともかく、個別の行動分析を行うことは非常に難しいです。
一方で、ちょっと危機感を持って何とかしなければならないと感じているのは、私たちの生活に密接に関係している「金融」という分野に対して、多くの人が極めて不十分な認識のままでいることです。
大学の講義で、「貸出によって預金を創り出す」という銀行の本質的機能(信用創造)の説明を行う際、多くの学生が最初は戸惑いを見せます。なぜなら、銀行は預かったお金を貸していると思い込んでいるからです。あるいは、「ゼロ金利政策」の舞台が短期金融市場(無担保コール翌日物金利)だということや、「マイナス金利」が日銀当座預金の一部に適用されていることなどは知りません。さらに恐ろしいのは、「インフレ」が良いことだと高校で教わっているという学生が極めて多いことです。実際、物価が上がることによって、現在の私たちは非常に苦しめられています。
さらに、「貯蓄から投資へ」の掛け声の下で、多くの国民が自らの資産を増やそうと投資に踏み出しつつありますが、金融収益の源泉を問わない投資行動が広がっていくことを懸念しています。つまり、自らの資産が増えた場合の収益はどのようにして生まれたのか、新たな成長分野に資金が回り、そこで生み出された利益の一部が投資家に還元されるのであれば何も問題はないのですが、流通市場でのキャピタルゲイン狙いの投資などの場合は、全体的な上昇相場を除けば、ゼロサムゲーム的な様相を呈することになります。上昇相場自体も、緩和マネーが市場に流れることで形成されている面もあり、経済全体がそれほど成長していない下で自らの資産が何故に増えるのかを真剣に考える必要があると思います。
今、金融教育の徹底が進められています。これまでお話したように、金融に関する知識・理解が不十分であるため、それが行われることは重要だと思います。しかし、金融教育の中身がどのようなものであるかが一番重要だと思います。今求められているのは、現代の経済の仕組みをしっかりと理解できる経済教育であり、その中での金融の役割をしっかりと理解してもらうことだと考えています。金融教育の中の投資に関する部分については、リスクをしっかりと教え、そもそも投資は余裕資金で行うものであることを徹底する必要があります。金融格差が拡大しつつある中、全ての人が投資によって資産所得を倍増するというのはあり得ないと思います。一部には投資に成功したという人や、実際に資産を増やしている人もいるかと思います。しかしながら、そうした人の個人的経験を全体に当てはめることはできません。「貯蓄から投資へ」というスローガンをイデオロギー的に受け入れ、多くの人が投資に躍起になっていく事態というのは非常に恐ろしいことだと感じています。
金融論というのは、お金儲けの学間ではなく、経済学の一分野であり、人間がいかに幸せに生きていくかを考える学問です。実学的なものと思われがちですが、今後いかなる人間社会を形成していくかを念頭に置いている点で、人間学的な側面が強いと思っています。
-今までで一番印象深い研究について教えてください。
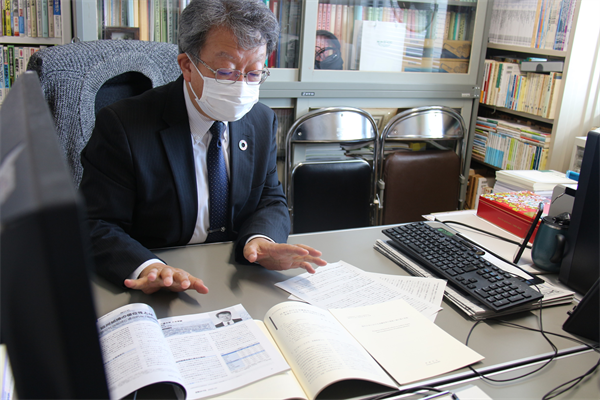
野崎銀行の公共性の検討ですね。銀行法の第1条には「公共性に鑑み」という文言が含まれています。宇沢弘文先生の「社会的共通資本」の概念にも「金融」分野が含まれています。私たちが豊かな経済社会を営んでいくためにはなくてはならない分野として「金融」が、私的利益の追求の場と化し、社会を混乱させるような事態を何度も引き起こしている今、その役割を再確認することが必要であると感じています。
現代社会における金融の役割をしっかりと理解し、そうした役割の発揮を通じて社会課題の解決に繋げていくことが必要だと感じています。今、金融教育に関する研究も行っていますが、海外などでは「個人」にとっての最適な状態を目指して金融教育が行われ、そのリテラシーの獲得が目指されています。当然、「個人」にとってという視点も大切ですが、金融のあり方は社会全体への影響も大きく、その視点を踏まえた上での金融教育が必要だと思っています。残念ながら現状では、「個人」にとっての投資教育へという流れが強くなっており、あるべき金融の姿を考えさせる教育、経済にとって求められる金融の役割を第一に教える金融教育が必要だと感じています。
-現在の金融業界で最も課題であると考えている点を教えてください。
野崎金融という分野が担うべき役割に即した規制の枠組みを再構築することだと考えます。競争政策一辺倒でなく、歴史的経緯および現実をしっかりと見て、金融規制を強化すべきだと思います。グローバルな観点から日本だけが規制をすることは無理だという意見もありますが、金融の競争政策に伴う弊害は、国際社会でも問題視されている今、日本が率先して金融規制を強化するということも必要だと思います。
-今後の目標や予定を教えてください。
野崎当面の第1の課題は、私の研究の出発点であった銀行資本の行動分析をまとめることであり、メガバンクグループや地域金融機関の行動分析を行いたいと思っています。現代資本主義社会における銀行の役割をまとめるという課題ですね。
第2の課題としては、金融分野におけるイデオロギー的認識に関する検討、「貯蓄から投資へ」や「資産運用立国」というフレーズの問題点について検討していきたいと思っています。イデオロギー論については極めて難解な面もありますが、人々の現実的行動を規定する力をイデオロギー的認識は有しています。科学的イデオロギーをそれに対置させ、社会全体の歩むべき方向性と金融のあるべき姿を重ね合わせていきたいと思っています。
研究者情報

人文学部 法律経済学科
教授 野崎 哲哉(NOZAKI,Tetsuya)
専門分野:金融論、銀行論
現在の研究課題:
日本の銀行業のあり方、金融システム改革と銀行経営、現代日本の金融政策、
地域金融のあり方、協同組織金融、フィンテック、SDGsと金融、金融教育
【参考】
人文学部HP https://www.human.mie-u.ac.jp/
教員紹介ページ(野崎 哲哉) https://kyoin.mie-u.ac.jp/profile/2265.html