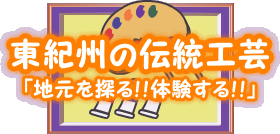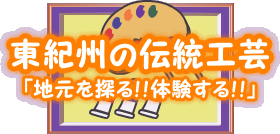| No.1 那智黒石 |
| 訪問日 |
平成12年8月5日 |
| 訪問場所 |
熊野市神川町神上 採掘作業現場 |
| 製品の特徴・歴史 |
那智黒石は、日本の中でも、熊野市の神川町でしか産出されない特殊な鉱石です。製品としては、墓石の原材料となるものが一番多く、その他のものとして、硯石、置物などとして使用されている。 |
|
| No.2 畑中木工(手作り家具工房) |
| 訪問日 |
平成12年8月5日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市 手作り家具工房 畑中木工(有) |
| 製品の特徴・歴史 |
畑中木工は受注生産を主としている手作り家具工房です。素材はすべて地元尾鷲で産出した広葉樹(主にトチ)やヒノキを用い、釘を使わない古くからこの地方に伝わる穴を開けて組んでいく方法で組み立て、最後に漆など自然の塗料で塗装仕上げをしている。 |
|
| No.3 大漁旗制作(万助屋) |
| 訪問日 |
平成12年8月19日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市 |
| 製品の特徴・歴史 |
大漁旗とは、普段船につけるもののではなく、新しい船のお披露目の時に、業者の方だとか船主のゆかりのある方たちが船主にお祝いの品として贈る旗だといいます。東紀州で制作しているのは万助屋1軒だけです。 |
|
| No.4 市木木綿 |
| 訪問日 |
平成12年8月28日 |
| 訪問場所 |
三浜町下市木 大久保織布工場 |
| 製品の特徴・歴史 |
市木木綿は縦じまがあるのが特徴で、夏は涼しく、冬は暖かい。明治初期から生産を始め、大正初期には盛況であったようですが、現在では2軒のみとなっております。 |
|
| No.5 尾鷲わっぱ |
| 訪問日 |
平成12年8月20日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市向井 尾鷲わっぱ 製造元 ぬし熊 |
| 製品の特徴・歴史 |
尾鷲わっぱは林業が盛んであった尾鷲で古くから作られてきた弁当箱である。表面に漆を塗ったもので夏は傷みにくく、冬は冷めにくい特徴を持ち、山林作業者に古くから愛されてきた。平成6年には県の伝統工芸品に指定された。 |
|
| No.6 尾鷲傘 |
| 訪問日 |
平成12年8月22日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市 河合屋 |
| 製品の特徴・歴史 |
骨組みが12本から出来ており、先端は布地の耳を使っている。布地を縫い合わせる時はミシンで2度縫いするが、残りの作業は手作業である。それにより、既製品よりも長持ちのするか傘が作られている。雨の多い尾鷲に適した傘です。 |
|
| No.7 ひのきアート |
| 訪問日 |
平成12年8月24日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市 |
| 製品の特徴・歴史 |
ヒノキのかんなくずを利用して創った、花・枕・マスク・のれんなど、とても面白い作品です。東紀州体験フェスタにちなんで、この地域のものを生かしたものとして考案された新しい製品です。 |
|
| No.8 御浜窯 |
| 訪問日 |
平成12年8月26日 |
| 訪問場所 |
御浜町神木 ピネ観光センター2階 (株)御浜窯 |
| 製品の特徴・歴史 |
御浜窯は今から40年余り前、窯元である神木の山中から陶長石が発見され、窯業試験場の指導を受け、昭和34年より地場産業を興す目的で、操業を開始し現在に至っている。御浜窯の特徴は、熊野灘の海の色を想わせるブルーの製品と那智黒石のような渋みを伝える黒を基調とした製品が特徴です。 |
|
| No.9 みはま小石 |
| 訪問日 |
平成12年8月9日 |
| 訪問場所 |
熊野市有馬町立石 (株)岡室碁石店 |
| 製品の特徴・歴史 |
みはま小石は、那智黒石とともに歴史は古く、熊野から新宮にかけての海岸で採取される石だけを「みはま小石」と呼びます。古くには、江戸にある紀州候の別邸の最高級の玉砂利として用いられており、また、神社の白い玉砂利用として用いられる場合も、最も評価が高いそうです。みはま小石の採取方法は手拾いのみで、1つ1つ厳選されるので、最高級品と評価されるのも頷けます。 |
|
| No.10 備長炭炭焼き |
| 訪問日 |
平成12年8月28日 |
| 訪問場所 |
尾鷲市泉町 MTエンタープライズ |
| 製品の特徴・歴史 |
窯出しの日であったので、話を聞く間もなく灼熱の窯に向かって窯だし作業を体験してきました。 |
|
   |