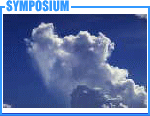|
東アジアの国際環境協力戦略と日本の役割
米本昌平
(三菱化学生命科学研究所科学技術文明研究部長・市民フォーラム2001理事)
I. 自然科学と国際政治の合体
21世紀の課題とされる地球環境問題の大きな特徴の一つは、自然科学の一分野である地球科学研究と国際政治の枠組みとが融合してしまったことである。これまで自然科学は政治とおよそ関係ないものと思われていたから、これは大きな変化である。例えば、気候変動枠組み条約という条約がある。1995年にベルリンで第一回締約国会議が開かれたこの条約は、地球温暖化に対処する目的の下にできあがったものである。
国際条約は、その冒頭でそこで使われる用語の定義を行うのだが、この条約では「気候変動」とか「吸収源」、「発生源」という言葉が定義されている。言葉の内容はここでは重要ではないが、これらは皆、地球科学の領域で使われている学術用語なのである。学術用語が条約の言葉遣いの中にそのまま繰り込まれている事実は、地球科学研究が対象にしている地球そのものが条約によって守られる対象になったことである。それは逆に考えれば、人類の活動全体が地球レベルの自然にまで影響を与えるものになってしまったこと、そして、これに世界全体が対応していかなくてはならなくなったことを意味している。
|